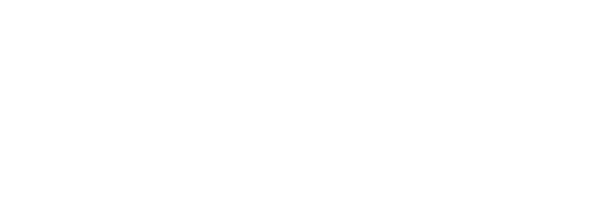今年の角川短歌賞は田中萃香の「光射す海」、道券はなの「嵌めてください」の二作に決まった。
>>
映画「娘は戦場で生まれた」の衝撃。この作品を観て得た熱量を原動力として想像と虚構を中心としつつ、ニュースや映画から得たものを織り交ぜながら受賞作を構成していった。読んでくださった方々の心の中に、なにがしかの感情を引き起こすことができたらとても嬉しい。
短歌をはじめたきっかけは曖昧なものであり、今も「短歌とは何か」という問いに何も答えられないまま作歌している。だから、今後も短歌を続けていくかどうかは分からない。ここまでかもしれないし、これからかもしれない。だが、言葉が好きだ。そして空想し想像する自分も好きだ。だから短歌をやめたとしても何年先も、言葉の想像力の力を武器にこの世界と対峙し続けたい。
角川「短歌」十一月号に掲載された、田中萃香の「受賞のことば」から。
想像、の一語に僕は立ちどまる。
シリアへ、と我が告げれば不思議そうに瞳を向ける友の多さよ 田中萃香
夕暮れの難民キャンプを抜け出した少年と見る光射す海
「光射す海」の作中主体は、取材のためシリアを訪れた日本人ジャーナリストである。
シリアで僕が思い出すのは、二年前に観た映画「ラッカは静かに虐殺されている」だ。地方都市ラッカに住む市民ジャーナリストたちの活動を記録したドキュメンタリーで、略奪と支配の連鎖に、ただ言葉を失った。
近年、シリアへの国際的な関心は高まっており、「娘は戦場で生まれた」も去年アカデミー賞にノミネートされた作品のひとつである。ちょうど日本ではコロナウィルスが流行り始めた時期の公開だったので、見逃したのが悔やまれる。
一連を読み始めてすぐに僕は、シリアにいま、日本人が行くことができるのだろうか? と単純な疑問を抱いた。十年前ならいざ知らず、ビザを取るのが困難をきわめるだろう。ましてジャーナリストであれば、命の危険に身をさらされることは明らかだ。外部と連絡を取るのも簡単ではない。
したがって僕は途中から、創作の可能性が高いと判断して読んでいた。そして先ほど引用した「受賞のことば」を見て、納得をした。
憶測だが田中自身、作品がよもや実体験と読まれるとは、想定していなかったのではないだろうか。ところが選考会の記録を見るかぎり、四人の選考委員は本物のジャーナリストの歌と読んで疑わなかったようだ。選考委員のひとり松平盟子は「現実に密着した説得力のある表現にどこか安心する」「現下のコロナの時代にあって、私たちはリアリティーを信頼し、リアリティーに縋って考えたくなる、そんな気がする」と述べ、作品の持つ「リアリティ」が選考の場で高い評価を受けた。
短歌の世界では、ときどきこういうことが起こる。亡霊が、変なスイッチを押したのだ。六年前に石井僚一が短歌研究新人賞に選ばれたときもそうだった。リアリズムの亡霊である。
ここで僕は、なにかを申し立てたいわけではない。
「ラジオ・コバニ」や「アレッポ 最後の男たち」、「シリアにて」など、現在のシリアを舞台にした映画は数多い。シリアが注目を集め、シリアが描かれるのは、戦後史上最悪の人道危機とも言われるその現場で何が起こっているのか、容易には伺い知れないからだ。
一般にリアリズムの価値は当事者性にある。
「いのち」の尊厳が問われる状況において、何を見て、何を感じたか。
だからこそ、当事者の信頼性が損なわれた作品は、ときに非難の対象にもなる。
田中がシリアを描いた動機は、どこにあったのだろう。当事者の声が届かない世界。ジャーナリストや映画監督がその地に惹きつけられたのと同じように、田中も短歌の実作者として、シリアを詠みたくなったのではないだろうか。
目の前に遥か広がる海峡の光より我に通じる道あり
離陸せよ雨降りしきる空港を 私の胸で燃えるシリアよ
出国の瞬間をドラマチックに詠んだ二首。想像の作品と知ってなお、作者の胸中に差し込んだ光や、燃えあがる炎、そのエネルギーをたしかに感じざるを得ない。
感じざるを得ないのだが、それでも疑問は残る。
「あまりにも生々しい」と拒否された通信社へと送りし写真
包囲の輪狭まりてゆくイドリブを生きた証に教える英語
たとえばこれら「生々しい」「生きた証」などの表現だ。特に「生きた証」は、すごく引っかかる。虚実の溝を埋めるには「生きた証」の慣用表現はいかにも軽い。もしくは重い。
まるで「自分は生きている」と訴える亡霊の声を聞くようだ。
いずれにせよ田中は、渾身の想像力をもってパラレルな「私」を詠いきった。ここが議論の出発点となるべきだろう。
僕自身の関心に引き寄せつつ言えば、選考委員の評価と作品のずれを解消するために、やはり、いまの若者の「想像」と「リアリティ」のあり方を考え直す必要があるのだ。
「光射す海」の一連が、新たな視点で読まれることを期待したい。
呼吸(いき)すれば胸くらみゆく秋寒の球体関節人形展に 道券はな
目を嵌めてください他人(ひと)のまなざしを受けて川面のようにかがやく
道券はなの「嵌めてください」は、人形の眼、人形の身体という主題が短歌の「人間性」を相対化していく意欲的な連作である。
人間と人形が真向かう「人形展」。そこから作中主体は人間の感覚と人形の感覚を行き来しながら、世界を新たな眼で塗り替えていく。
ほの昏い展示のなかで人形はかがやく凛と死から隔たり
暖房に汗ばむ身体生きるかぎり朽葉のような匂いをはなち
「いのち」を持たない人形のたたずまいは、人間の「いのち」の重みを浮かび上がらせる。二首目「生きるかぎり」の字余りが、その重たさを読者に伝えているだろう。
個人的な感覚の話をさせてもらえれば、僕は「人形」が好きではない。理由の半分は、脳が本能的に「人間」と見做したものを打ち消す、認識の不安定さに由来する。動物のぬいぐるみは可愛いと思う一方で、人間のかたちをした非人間的なものは、おそろしい。AKBグループの人たちは、僕にはみんな人形に見える。
連作の前半は、相聞歌らしい相聞歌だと思いながら読んでいく。身体感覚。「あなた」への感情。それらが次第に、人形の世界に取り込まれることで異様な変容を遂げる。
人形は淡く微笑む抱かれたら抱かれたままに歪む身体で
硝子玉を眼窩に嵌めた人形よ見るとはひしとせめぎあうこと
人形自身は、何をするわけでもない。抱かれるまま、見られるまま。受動に徹し、しかしその眼は、人間を見つめ返しているようでもある。
自然を写す、人間を写すという近代短歌が掲げたテーゼは、つまり「いのち」を見つめることであった。「いのち」のない無機物を見ることは、近代的なリアリズムと対極にあるように思われる。
椅子として生まれたかったがたついてあなたに布を嚙ませてもらう
椅子を擬人化したような歌。ユニークな着想の一首だけれど、ここにあるのは「人形」になる倒錯したよろこびではないだろうか。「布を嚙ませる」は慣用表現だが、こう描かれると、なんとも言えない官能性が立ち上がってくる。
野葡萄も熟せばだれか摘みにくるそれまで膝を閉じていなさい
夜更け過ぎビスクドールはその頬に延べられた手を拒まずにいた
暑苦しい乳房(ちぶさ)を脱げばさえざえと硬貨のようないのちが残る
人形の受動性は、もうひとつ、人間の暴力性をもあぶり出す。特にそれが男性的な暴力であることは、多言を要しないだろう。僕は亀井亨監督の映画「無垢の祈り」を連想した。
三首目は文字通りに、乳房そのものを脱ぐ歌と読みたい。「硬貨のようないのち」をどう読むかは難しい。僕はなにか少女性のようなものの喩かもしれない、と考えているのだが、どうだろうか。
いつかいつか羞(やさ)しいあなたを立たせたい老衰という眩しい水際
連作のクライマックス。老衰とは、人間の「いのち」の果てである。
選考会では作中主体が「人形」で、老いた「あなた」を詠んだと考えた人もいた。もちろん二人とも「人間」という読みもあるだろう。僕は「立たせたい」あたりから、「あなた」も「人形」になってしまったような陶酔が感じられる気がする。
ゆっくりとまなじりを上げ見つめれば祈りの声なき国の紅梅 田中萃香
明日事故で亡くなるひとはいま何をしているだろうこの秋晴れに 道券はな
田中の連作、道券の連作、その生々しさは、どこから来るのだろう。
想像力、と僕は繰り返す。
田中は遠くジャーナリストに成りかわり、道券は人形の眼で「人間」を思う。作者が「作者」を離れたとき、そこに「人間」は存在するのだろうか。「人間」のいない場所で、はたして歌は成立するのだろうか。