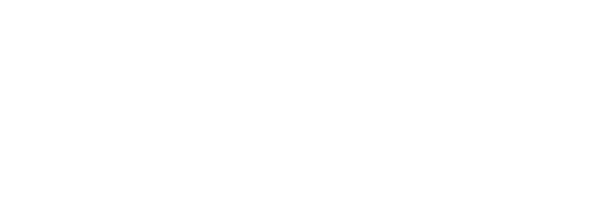今年も短歌研究新人賞の受賞作が発表されました。新人賞はゴールではなくスタートで、受賞者はこれから受賞者として、作品が歌壇の正典に加えられるべきか否か繰り返し問われることとなります。受賞しなかった人は候補に残ったことに手応えを感じたり、あるいは選考座談会の議題にのぼらなかったことに地団駄を踏んだりしているころかと思います。私は毎回大変に悔しがっていました。いずれにせよ、応募された皆さんはお疲れ様でした。受賞できない悩みについてはこのコラムの第二回後半で扱っていますので、よければそちらもご一読ください。皆さんに良き短歌ライフがありますように。
*
さて、今回扱いたいのは文体についてです。2024年の第67回短歌研究新人賞において問題となったのは、受賞作である工藤吹「コミカル」の文体が受け入れられるものなのか否か、でした。黒瀬珂瀾と石川美南が議論を交わしている箇所を引きます。
黒瀬 皆さんのご意見にはまったく賛成だけど、僕が点を入れなかった理由はただ一つ。この作品の韻律が受け入れられなかった。破調というか、字余りが不用意に見えるし、それでいて全体に平板な感がある。〔後略〕
石川 私はもうちょっと韻律感があると受け取りました。〔中略〕文体レベルでも水の流れに従っているというか、コップの水が溢れるぎりぎりのところを見極めようとしている。
〔中略〕
黒瀬 そこらへんを受けて言うと、シームレスな構造でも、山階基さんとかの文体はとてもいいと思うんだけど。
-「第67回短歌研究新人賞選考座談会」『短歌研究』2024年7月号
ここで「文体」と呼ばれているものは、作品の破調など韻律に関することがらです。短歌は五七五七七の5句31音から成る定型詩である、といった言葉が建前であることはもはや自明でありながら、それでもその定型からどの程度離れてよいかは問題となり続けています。最終的に黒瀬は「コミカル」への反対を「僕一個人の韻律意識にこだわった結果」として、受賞に賛同しました。具体的な作品を見てみましょう。
住宅の並びにあれは給水塔、まるで二十世紀の近未来
遊具でのあたらしい体勢を披露した 私たち秋の運動公園で
-工藤吹「コミカル」『短歌研究』2024年7月号
引用歌はともに下句で字余りと句またがりが使われています。一首目は「まるでにじゅっせい/きのきんみらい」と8音+7音、二首目は「わたしたちあきの/うんどうこうえんで」と8音+9音に句切れるかと思います。句切り方は感覚的なものなので、違うやり方も想定はできますが、ここにあまりこだわってもしょうがない。問題はこの作品の是非ですから。
書かれている内容に注目すれば、二首ともおもしろい歌であると思います。一首目は現実世界にレトロフューチャーの実感を重ねることで、日常生活を異化するうれしさがあります。
対して二首目はかなり情感の薄い内容で、ともすれば瑣末報告歌に見えるかもしれません。けれどもこの歌は「私たち」が読みのとっかかりとなります。遊具でのあたらしい体勢を披露した「私たち」がいる。その「私たち」が秋の運動公園にいる。意味内容的には「私たち」は二回繰り返されるはずです。しかし実際に遊具にいる「私たち」があたらしい体勢を披露したのは一瞬のことです。その一瞬が、短歌の意味の中では二回反復されている。引き延ばされた時間は「私たち」の中に収斂していきます。日常の瑣末な一瞬を微分して、一瞬の加速度に焦点をあてる点がこの歌の魅力なのでしょう。
工藤吹作品の情感の薄さは、𠮷田恭大や鈴木ちはねの系譜に位置づけることができます。上の世代からは淡いと言われがちであまり理解されないこの二者の文体はどういったものなのか。作品を引きつつ少し考えてみます。
霊園が避難場所にもなっている いつか霊園に避難するとして
もともとはコンビニというわけではない物件にも入るコンビニのすべて
-鈴木ちはね「そばの花」ウェブサイト「歌とポルスカ」2022.03.02公開(どのような種類のセンシティブな内容や不安にさせる内容ですか?)
非常時はかまどになるベンチがあって町内会が年一でする
-𠮷田恭大「否定形と提携」『現代短歌』2023年11月号
情感の薄い作者の中でもさらに情感の薄い歌を引いてきました。私はどれも良い歌だと思います。鈴木ちはねの一首目における霊園という死後の集合住宅は、日常の集合住宅との対比ですし、避難という非日常との対比にもなっています。二首目のほうも、どこにでもあるコンビニの、どこにでも入居可能な可塑性が、それこそプラスチックの可塑性のように提示されています。
𠮷田恭大の一首目は、定型句を短歌定型に押し込むことで、定型句自体を聞いたときに自覚する様々な情感への内省を促す構造になっています。二首目では、鈴木ちはねの「霊園」と同じく、「ベンチ」と「かまど」という一見するとミシンとコウモリ傘(※1)くらい離れている二つのモノが、非常時に結びつく驚きがあります。しかしながらこれらの情感は一読して即座に理解可能なものではなく、少し考えてみなければその良さにたどり着くことは困難です。
ところで短歌研究新人賞の受賞作発表号である『短歌研究』2024年7月号には、作品季評として、青松輝による𠮷田恭大評が掲載されています。この作品季評座談会にはコラムの書き手である髙良も出席していたのですが、実際に話しているときから気になっている発言がありました。私は𠮷田恭大の文体に郡司和斗との近さなどを感じたと話していて、それを受けての青松の発言です。その箇所を引きます。
青松 髙良さんが郡司さんを感じたと仰ったのが何かというと、僕は、今ニュートラルっぽく見えている口語短歌に潜む、男性的な自意識のようなものだと思っています。一旦判断を保留する手つきがある。郡司さんや𠮷田さんだけじゃなくて、近しい世代、少し上だと斉藤斎藤さんや永井祐さんからの文脈があって、最近だと鈴木ちはねさんなどの笹井宏之賞の候補になっているような短歌にもそういう流れがある。もちろん男性以外の書き手にもよく見られる作風ですが。
-「作品季評第130回〈後半〉」『短歌研究』2024年7月号
ニュートラルな口語短歌の文体に、「男性的な自意識のようなもの」を読み取ってしまうのはなぜなのか。文体は文字上のものであって、書き手のジェンダーとは直接結びつかないはずだろうと思います。
実のところ、青松の発言は睦月都の歌集との対比の中ででてきたものです。睦月の歌集について青松は、作品季評4月号掲載分(※2)で以下のことを言っています。
青松 僕はわりと透明な口語、に見えるような短歌作品を書くのですが、それに対して睦月さんは装丁も文字組も昔の短歌っぽい手法で、透明な文体で書かないことで、弱い者の立場に寄り添って異議を唱える。川野芽生さんや大森静佳さんも同じ系譜とみていますが、古典的なものを使うとある種の権威的な振る舞いになってしまうのですが、そこが逆説的になっていて、マイノリティの側に立つためにあえて古い権威的なものを見せ消ち、括弧付きで引用してくる手つきです。
-「作品季評第130回〈前半〉」『短歌研究』2024年4月号
文体の話をしているはずなのに、挙がっている名前は睦月都、川野芽生、大森静佳と、女性歌人ばかりです。透明でニュートラルな口語寄りの文体に男性的な自意識を感じ、対して古めかしい文語寄りの文体に女性歌人の名前ばかりを挙げてしまうのはなぜなのか。私は文体の話をしたいのに、いま問題になっているのはジェンダーであり、男女であり、歌人の肉体です。どうして文体を問題にしたはずが、肉体という物質のことを考えてしまうのか。問題=物質となる短歌文体とはなにか。ここにフェミニズムの理論が介在する余地があります。この謎を解くために、少し回り道をしましょう。
ジュディス・バトラーの『問題=物質となる身体』(原題Bodies That Matter)では、前著『ジェンダー・トラブル』で提示されたテーゼ「セックスはつねにすでにジェンダーである」に対して、身体の物質性の問題を問う反論が寄せられたと書かれています。身体的性別と社会的性別が同じものであるならば、私たちの肉体的の問題は捨象され、言葉の戯れになってしまうのではないかと。
さて、身体的性別はどのように出現するのかについて、バトラーは次のように語ります。
主体形成は「セックス」の規範的《幻想》[phantasm]との同一化を必要としており、またこの同一化は、棄却領域を生み出す排除――それなしでは主体は出現できない――を通じて行われる。これは「棄却」の誘因を作り出し、主体を脅かす亡霊というその地位を作り出すような排除である。さらに言えば、所与のセックスの物質化は主として同一化実践の統制(傍点)に関わるため、セックスの棄却への同一化は執拗に否認されることになる。
-ジュディス・バトラー『問題=物質となる身体:「セックス」の言説的境界について』(2021)序章
だいぶ難しい話が書かれています。まず「主体」が厄介です。バトラーはこの前提として、身体的性別は主体形成と同時に出現することに言及しています。ならば主体形成に関する力学がどのように働いているのか。その答えが引用の箇所なのですが、今度は「棄却」とは何かに頭を悩ませることになります。これは「規範的《幻想》」と対比されるもので、規範的でないと棄却された外部、つまりクィア的な存在と主体が同一化することが否認される作用があると語られています。同時に、こうした否認の過程が主体形成に含まれていることに、規範を撹乱する契機があるのだと、本書の中でバトラーは議論を展開していきます。
回り道はこのへんにしておきます。では、短歌の「作中主体」はどうなるのでしょうか。バトラーは規範的幻想について語っていました。幻想……。規範的幻想に抗うにはどうしたらいいのでしょうか。
そういえば、「幻想はあらがう」と題された座談会がかつて開催されたことがあります。『文藝春秋』2022年5月号の「幻想の短歌」特集です。出席者は、大森静佳、川野芽生、平岡直子の三人です。奇しくも、この座談会に登場する面々は青松輝が挙げた名前と大きく重なっています。これは偶然ではありません。ここで歴史的想像力を働かせてみましょう。
近現代短歌における女性歌人の歴史は恋愛の歌から始まります。しかしながら明治末期の自然主義の到来以後、短歌のデフォルトの主体は人間=男性が想定されるようになり、女性歌人たちは自身が「女」であることを作品内で自己言及するようになります(※3)。
戦後の1950年代には女歌の時代があり、反写実的な幻想の短歌が出現します。このうち葛原妙子と山中智恵子は前衛短歌に組み込まれ、歌壇的評価を得ることになりました。
1960年代の末になると、河野裕子が妊娠する身体を詠み、短歌が記述可能な女性性の領域を広げました。しかし同時に、短歌的な女性性の合意が社会一般的なそれの反復になることへの懸念から、1980年代には女歌シンポジウムの時代が訪れます。
またこの時期には短歌の読みに関する大きな地殻変動も生じています。『短歌研究』1987年12月号の年末回顧座談会の中で、馬場あき子は『塚本邦雄湊合歌集』(1982)や『岡井隆全歌集』上下巻(1987)に年譜が付されていることに触れつつ、「そういう履歴書ごと鑑賞する場面っていうのを解禁したっていうことになるでしょう」と発言しています。前衛短歌においては、作者と作中主体は切り離されて鑑賞すべきであると考えられていましたが、この発言からもわかるように、読み方の制約に関する魔法がこの時期に消失しました。
結果として、80年代登場の女性歌人は、恋愛・結婚・妊娠・出産に関する歌を歌集に収録することが、ひとつの典型として成立するようになります。恋愛に関する歌の時期が長かったとはいえ、俵万智もその一例にすぎません。例外は、鬼という幻想を文体に取り込んだ馬場あき子と、あるいは変身する身体を提示する水原紫苑などでしょうか。
水仙の青き葉蔭にわれあらばまさびしきまで性なきひとり
喉まで蜻蛉つめて逢ひにゆく死者より深くきみを愛すと
-水原紫苑『うたうら』(1992)葡萄熟るる熱き大地にへしみつつ乱舞異形の鬼は群れゐ
つゆの身のつゆの世ながら狂ふべし鬼ならば青き精神の鬼
-馬場あき子『青椿抄』(1997)
水原紫苑の歌では自分自身の性的特徴が、身体を異形に重ねることで無化されています。馬場あき子の一首目は「へしみつつ」が解釈に困りますが、古語の「へす(押しこまれる)と「見る」の合成で、下から見上げている様子ととりました。この連作は鬼剣舞を観ているもので、それを観る中で、二首目では自分自身の精神の鬼を内省しています。
2010年代末以降、若手歌人の間では自身のプロフィールを読みに介入させないようにする動きが見られました。上の世代の歌人からは、私性の希薄化などと呼ばれたのですが、この動きは80年代に消失した前衛短歌の魔法を再起動する動きだったのではないかと考えることもできます。そうした若手歌人の中で、水原紫苑が帯文や栞文を寄稿している歌人には、平岡直子、川野芽生、睦月都、榊原紘などがいます。幻想特集での座談会の出席者や、青松輝が挙げた名前と重なる部分があるのは、偶然ではないでしょう。
ひとの身につかのま碇下ろしゐる魂よわが湖底痛めり
-川野芽生『Lilith』(2020)飛行から遠きわたしに収まらず鳥が羽ばたきをくりかえす
-平岡直子『みじかい髪も長い髪も炎』(2021)しゃがむときからだのなかで鳴る骨を双子の姉のようにおもえり
-大森静佳『ヘクタール』(2023)から風のやうな言語で喋りたりたがひの家の猫の話を
-睦月都『Dance with the invisibles』(2023)百合のように俯き帽子脱ぐときに胸に迫りぬ破約の歴史
-榊原紘『koro』(2023)
これらの作品では、自分自身の身体が客体として再認識されるという特徴があります。川野の歌では肉体という魂の牢獄を踏まえて、自分自身の中に巨大な湖を幻想しています。平岡の歌では、本来収まるはずのない鳥が体に収まる様子を見せ消ちすることで、身体が異形に見える感覚を引き出しています。大森、睦月、榊原のそれぞれの歌でも、擬人化の逆のような形で、身体が擬似的に別のモノに喩えられています。
相田奈緒は上記のような擬人化の逆の表現に対して、「重ね合わせの瞬間:比喩的アニミズム表現の可能性」『短歌人』2023年9月号の中で興味深い内容を示唆しています。曰く「この疑「無生物」化とも言える表現は、現実の人間の身体への抵抗あるいは開放でもある。〔/〕そしてこのことは、繰り返しになるが、即座に反転しうる。生命感を人間のみに限定しない、というアニミズム的心性に親和すると私は考える。」と。
アニミズム、つまり自然空間から神秘性を取り出すことは、人間社会の当たり前を揺さぶる上で、有力な基盤となるはずです。そして現代の口語が透明な文体になった状況で、こうした固めの文語的文体は奇妙なものと言えるかも知れません。すると、これらの作品からは、文体をクィア化する作用を引き出すことができるのではないでしょうか。それが成功するか失敗するかは、作品を見て、その都度考えていく必要があるでしょう。文語と幻想とが重なる地点には、身体を開放する聖域を作り出すことができるのかもしれません。
短歌は短いために、読みに際してはあたりまえ、常識、共同幻想の文脈が多重に介在することとなります。そうした幻想と、歌人の試みる幻想との衝突する場が文体です。だから「短歌文体that matters」、問題=物質なのは短歌文体だ、という議論は、これからも尽きることはないでしょう。
【註】
※1 ロートレアモン伯爵の詩の一節である「解剖台の上でのミシンとコウモリ傘の不意の出会いのように美しい」は、シュルレアリスムにおける詩的飛躍の例を説明するものとして、しばしば引き合いに出されます。
※2 作品季評は一般的に連続で掲載されるものです。今回4月号の続きが7月号掲載と時間が空いてしまっているのは、『短歌研究』5+6月号が作品特集号として全ての連載を休止したためです。
※3 人間=男性という作中主体が想定される中で女性歌人がどのような作品を作ったのか、またその力学の問題点などについては、『短歌研究』2023年4月号ハラスメント特集にて「歌人の顔はどんな顔か:短歌における私性とフェミニズム批評の試み」と題した拙論を掲載しています。