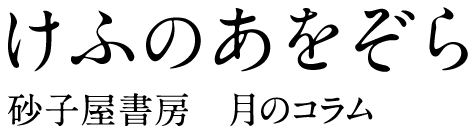「けふのあをぞら」というタイトルで、拙い文章を綴ることとなりました。
よろしくお願い致します。
零歳の時を一回目として、七回目の午年を迎える前期高齢者です。長年、俸給生活者として生きてきましたが、今もアルバイターとして平日の朝は、おおよそ出かけています。露地を抜け、道路に出ると空を見上げます。雨や曇りも嫌いではないのですが、四季それぞれの青空はやはり気持ちがよいです。生きている確認作業のように空を仰いでいます。鳥の声も、35年ほど前にこの埼玉の地に移ってきた時より減った感じはありますが、聞こえます。今はヒヨドリやヤマバトが多いです。ヤマバトの声は好きで、聞き惚れてしまいます。また今年は残念ながら聞けなかったのですが、モズの声を聞くと、心が高みに昇る気がして何か得した気分になります。
そういう日々に感じたこと、思ったことを記してゆくつもりで、この題をつけました。よろしくお願い致します。
それにしても、えらいことを引き受けてしまいました。文章を書くのは苦手です。
どこかで、にっちもさっちもいかなくなったら途中退場があるかもしれません。先にお断りしておきます。
「コレ、ダレ?」と言われそうですので、自己紹介しておきます。
上條雅通と申します。雅道とか上篠とかと誤記されることが多いです。名前を間違えられるのは、間違えられる方の責任と思っています。
1954年1月5日東京生まれ。1976年に岡野弘彦主宰「人」短歌会に入会。1993年、同会解散後、藤井常世が創刊した「笛」に参加しました。2013年に藤井が急逝したのち、仲間と「笛」を続けて今日に至ります。歌集3冊を出したのみで、特筆すべきことはありません。また、所謂、歌壇のことはよく知りません。
二十代後半の頃だったか、短歌系出版社の手帳の宣伝文句に「歌人の方に、短歌愛好家の方に」というのがあり、「はて、自分はどちらなのか」と考えたことがありました。現時点について言えば、実力、勉強の量、生き方、いずれをとっても歌人などとは言えないと思っています。
最近、と言っても、ここ数年という単位ですが、大変感激した本のことを記します。
篠田謙一著『人類の起源』(中公新書、2022年)です。著者は近年盛んになった分子人類学という分野の研究者で、国立科学博物館館長です。従来、人類の歴史を、発掘された骨の化石の形態等から探っていましたが、骨の化石から抽出したDNAを解析し、遺伝情報を手がかりに考察する学問です。私は書店の店頭で手に取って購入しました。2023年新書大賞第2位に入った本だったというのは、読後に知りました。最先端の学問の内容をわかりやすく、かつ読者の想像力に働きかけるように語っています。と、言っても、私などには専門的なところ、特に技術的なところ、ハードウェア、そしてデータ分析の手法などでわからないことが多くありました。読了した数ヶ月後、出張先の金沢の書店で本書を見つけて購入し、再読しました。もっとよく知りたいという思いがあったからです。
語りたいことは沢山あるのですが、一つを上げるなら、ホモサピエンスとネアンデルタール人、そして、デニソア人が同時に存在していた時代のことです。ホモサピエンスが優位になり、ほかの人類は滅びるわけですが、共通の祖先から別れながら、また、交雑があったことも遺伝子解析から、わかっているようです。
物事を例え話で考えるのは、軽々に行なってはいけないのですが、このくだりを読んでいて、古いと言われる形で歌を作っている私はネアンデルタール人で、最近の若い歌人たちはホモサピエンスなのかもしれないなどと考えてしまいました。
今の若い方々の短歌観とか、どのように歌を作っておられるか、私は不勉強で、よく知りません。ただ、この「月のコラム」の高良真実さんの「夢からうろこ」を読んでいてはっとすることがありました。2024年12月1日付の「人工知能は名歌秀歌の夢を見るか」で、田中有芽子さんの歌集について次のような注を付けられています。
田中有芽子『私は日本狼アレルギーかもしれないがもう分からない』は、2019年に私家版として刊行されたのち、2023年に左右社から新装版として刊行されました。私家版歌集が編集者の目に留まり、商業出版された事例はいくつかあります。短歌の世界の人口が増えたことで、賞に拠らない歌集出版の道が生まれつつあります。ただし、受動的な態度のままでは何も起こらないでしょう。
これを読んで、そうなんだと思いました。まず、賞に拠る歌集出版というものが普通にあるということ。そして、賞に拠らない歌集出版も出てきたということです。「短歌の世界の人口が増えた」というのは、マーケットが大きくなってそこに企画出版(自費出版ではない出版)による出版ビジネスが存在できるようになったということと考えられます。出版社の努力もあったと想像します。時代が変わったということでしょうか。
数年前のある日ある夜、テレビ東京のワールドビジネスサテライト(WBS)を見ていたら、枡野浩一さんをゲストに迎え「なぜいま短歌が”バズる”のか」という企画がはじまり、「歌人が出ている!」と驚いて見入ったことがありました。「なぜ若者が短歌に熱中するのか?」を分析し、企業はそこにどうビジネスチャンスを見つけるかという内容だったように憶えています。短歌が経済あるいはビジネスの価値観の中で評価され、本当の意味でプロの歌人が出てきているということを知らされました。調べると2022年11月4日のことでした。
ただこの番組について一番印象に残ったのは、最後に、これからの展望を問われた枡野さんが、旧勢力の反撃があるだろうというという趣旨のことを言われ、司会者がキョトンとした顔になった場面でした。
それはともかく、歌人が経済ニュースの番組に出ていることに驚きました。プロフェッショナルの世界がはじまっているとその時感じました。
勉強して、精進して、賞を取り、歌集を出す。あるいは出版社の編集者の目にとまるようにする。そうやって自分の短歌を磨き、ひろめてゆくわけですね。昔、歌だけで食っていたのは若山牧水だけだいう話を聞いたことはありますが、プロの歌人というのは、短歌史上あまりいなかったような気がします。それはともかく、プロの世界ですから厳しいでしょう。競争も激しいのかもしれません。高良さんの「ただし、受動的な態度のままでは何も起こらないでしょう。」の一言にそれが感じられます。
そして、そうした歌人の在り方だけでなく、趨勢として、今日作られ、鑑賞されている短歌自体、変質しつつあるように思われます。ここ4、5年、投稿短歌の選に少し関わってきました。一般からの投稿作品から良いと思うものを選び賞を授与する催しです。投稿作品の多くが現代語の短歌です。仮名遣いももちろん新仮名が圧倒的です。そういう時代が来てしまったと何度かため息をつきました。
このことから、この作者の方々の多くは、文語旧仮名の短歌などは読まないと想像されます。文語旧仮名で歌を作る人は、ネアンデルタール人のように消えてゆくことになるというのが、冷静な予測でしょう。
文語短歌についての批判はあれこれあります。文語短歌はコスプレだ。現代語で暮らしている国民に対して失礼だ。そもそも現代の短歌で使われている文語はまがいものだ。あるいは、用語の問題ではありませんが、古典を振りかえるのは保守反動的という指摘もありました。
そういう言葉を聞いていると、もう、お互いが見えない距離まで離れた方が良いのではないかと思ってしまいます。
またまた、例え話で恐縮ですが、短歌を一つの細胞として見ると、環境の変化に対応する新しい部分が出来てきて細胞分裂が起こり、気がつくと分かれた細胞が隣に並んで泳いでいたという場面が想像されます。そうすればお互いすっきりするでしょう。私が乗っている古い方の細胞は新しい環境に対応できず、衰え、滅んでゆく運命にあるとしても……。まあ、平家となって美しく滅びん、です。
最後に、『人類の起源』にもどりますが、その「終章 我々はどこから来たのか、我々は何者か、我々はどこに行くのか-古代ゲノム研究の意義」は著者が力を込めて書いたと思われる文章です。著者の専門的な知見からすれば、「人種」という言葉は意味が無く、ホモサピエンスはただ一種であります。「民族」という言葉は固定的な何かではなく、流動的なもののある時点での姿です。例えば、日本人は、旧石器時代人、縄文人、弥生人が入れ替わったり、包含したりして出来てきたわけで、ずっと同じ集団が居続けたわけではありません。著者は、人種や民族という言葉で、差別や偏見、そして紛争や戦争が起きることの愚かさを説いています。科学は素晴らしいと思いました。
今日は、午後から晴れて、寒い一日でした。目に入った次の一首を私へのはげましとしとして引用させて頂きます。
きはまれる青天はうれひよぶならん出でて歩めば冬の日寂し
佐藤佐太郎『星宿』