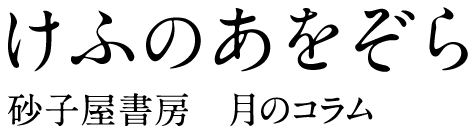広坂早苗の第2歌集『未明の窓』を読む。広坂は県立高校の教員である。教室現場を素材にした歌を読みながら、いろいろと思うところがあった。
教師が詠んだ学校の歌というのは、山のようにある。すぐに口について出るのは、
佐野朋子のばかころしたろと思ひつつ教室に行きしが佐野朋子をらず
という小池光の歌。この歌については、短歌愛好家のみならず短歌に興味のない人にも知られていて、ネット上で議論されている。困った奴だが憎めない、さりとて放ってはおけないし……。いやいや、今日こそは一発かまさねばなるまい、と教室へ出かけて行ったら居ないではないか。教師に全く威厳がない。島田修三風に言えばトホホ的感情が横溢する一首。「ころしたろ」と言いながら、佐野朋子はなかなかに愛すべき存在であり、教師にも余裕がある。
教師を主人公にした小説や映画、漫画も数えきれないほどあるはずだ。「青春とはなんだ」なんていうテレビドラマは、家族で見ていた記憶がある。いわゆる熱血教師もの。ネットで調べたら、1965年から1966年にかけて日本テレビ系列で放映されていた由。さりとてとくに印象に残った場面はない。一番上の兄が主演の夏木陽介の髪型を真似して、ドライヤーを吹きかけていたことが思い出される。
教師ものの映画で心に残っているのが、「下り階段をのぼれ~Up The Down Staircase」。大学時代の暇なときに名画座で観たのかと思ったが、1967年に公開されているから、中学校の頃に観たことになる。そういえば、テレビ放映で観た記憶がおぼろげによみがえる。居間で寝転んでいたのが、やがて引き込まれるようにテレビの前に釘づけになったのが、この映画だったかもしれない。
こんな映画、誰も知らないだろうと思っていたら、中村うさぎがウェブ上で取り上げていて、ちょっとうれしかった。「うさぎの映画天国」というサイトで、実に的確にその魅力を伝えている。全文引用したいくらいだけれど、長いので、その言葉を借りて紹介したい。
ニューヨークはハーレムの荒れた高校が舞台。主人公は理想に燃えた新任の女性教師シルビア。担任のクラスには、不良やバカ騒ぎする生徒、不登校の生徒もいる。格差社会の底辺の家庭の子供たちなのだ。授業以外にも雑務が山のようにある。今の日本の状況と変わらない。アメリカが日本の20年先を行っていると言われた時代。懸命に生徒と向き合う主人公だが、ある生徒の自殺未遂に責任を感じて、志むなしく転属を願う……。だがその矢先、一人の生徒が、彼女に心を開く。彼女は転属願いを破り捨て、下り階段を上って教室へ行く。うさぎ曰く「タイトルの“下り階段をのぼれ”とは、下り専用の階段を規則を破って逆にのぼることで“慣習や規則に囚われず自分の信念を貫け”という意味が込められています。」
1960年代の後半に、その時は気がつかなかったが、教師ものが流行っていたらしい。それで、ふたたびネットを検索すると―。グーグルに「第1部日本の教育史の概観」というのが見つかり、1960年代後半の記述を読んでみた。その時期は、高度経済成長期で雇用が拡大し、家計も安定、都市部に中流階級が拡大した。教育の面では学歴主義の風潮が盛んになり、進学需要が高まったとある。一方で、詰め込み、受験戦争、落ちこぼれが問題としてあがってきた。OECDの教育調査団が日本に来て報告書を残したが、その一節がなかなかにきびしい「18歳のある一日にどのような試験成績をとるかによって、彼の残りの人生が決まってしまう」。進学需要と教育への危機感が、小説や映画、漫画、あるいは雑誌などの実際の需要を生んだようである。この映画はハッピーエンドではないし、ドラマチックでもないと中村うさぎは書いている。自分の記憶に残った場面はほとんどない。だが、下り階段を上るラストシーン、ここは自分も覚えていて、そこにはたしかに希望へのメッセージがあった。
それからおよそ50年。広坂早苗の『未明の窓』を読む。
用を足す男子生徒を追い立てて水撒き始む北の隅から
四階西便所の床をきよめゆくひとりなれども山が見ている
教職の奥の深さよなじみなき小の便器も磨き慣れたり
男子トイレに便器を擦り水を撒きこころならずも愉しくなりぬ
便所掃除の当番に当たっている生徒は、いつだってサボタージュ。監督の先生は事を荒立てることなく、自分一人でやる。怒りと自分のふがいなさに忸怩たる思いは免れない。でも、3,4首目にはそれを引き受ける余裕が感じられる。「教職の奥の深さよ」とか「こころならずも愉しくなりぬ」とかいう措辞は、そのあたりの消息を物語る。
けれど、そんな余裕もやがてなくなる。
明日よりはもう会わぬこと最大の賜として卒業の日過ぐ
制服のコサージュ胸にはなやかに式場に入るガム噛みながら
「証書授与」ひとりのひとりの名を呼びてめっぽう明るしわたしの声は
煙草を賭け点数争いせしことを「青春だった」と言う生徒たち
睫 濃く胸をひらいて街へゆく女生徒達よGood Luckさらば
花一輪贈らるるなき別れをし教室の床にガム剥がしおり
窓枠に残る卑猥な落書きを黙々と消す呪詛消ゆるまで
卒業式過ぎて誰かの置きみやげ帯状疱疹ふつふつと湧く
青春娯楽番組「青春とはなんだ」や映画「下り階段をのぼれ」の舞台もかくやと思われる。50年前となんにも変っちゃいない。この歌集にあらわれる先生が、夏木陽介演じる熱血教師野々村やサンディ・デニス演じる新任教師シルビアではなく、端役としても映らないだろう平凡なベテランの、敢えて悪く言えば、薹の立った女性教師だということだ。彼女はことを荒立てず、規範意識の希薄な生徒を卒業に導くことに頭を悩ませ、秩序の維持を優先する。そして、心身を痛め尽くす。
そんなことに同情できない、と言う声があることも、彼女は十分に承知である。卒業式に生徒がガムを噛むのくらいやめさせられないのか、未成年が煙草を賭けるなんて許していていいのか、生徒を呪詛するのは教師の適性に欠けるんじゃないか。先の歌をあげれば、こういう声が出ることは、予想される。
そう、だからこういう歌は、現役教師によってうたわれることが少ない。教師はこうあるべきだという世間の目を意識するからだ。
この歌集にうたわれているような教師は、世間から求められていないし、場合によっては非難されかねない。あなた、それでも先生ですか!
作者はそのことを痛いほど分かっている。その上で、この歌集の先生は、そのような世間の目に応える立派な先生から、脱け出してうたった。私の卒業した高校もそんな風だった、現役の頃にはそんな高校で教えたこともあったよ、と言う声もまたいっぱいあるはずだ。作者は荒れた教室をうたったが、今の教育に関する批判や非難めいたことを訴えたわけではない。この歌集にうたわれた現実は、50年前と変わらず、また、いまさらとりたてて騒ぐことでもないと作者は思っているに違いない。これらの歌に訴える力があるとすれば、それはそのような現実に生きる孤独な葛藤を、誤魔化さずにうたっているところだと思う。教員という職業にまつわる、こうであらねばならないという社会の圧、自己の倫理観の圧から脱け出てうたうこと、それが誤魔化さないでうたうという意味である。自己の感情を、とらわれることなくうたうことが、作者にとっては重要なモチーフだったのだ、と自分には思われる。
歌集『未明の窓』には、子どもを詠んだ佳作がある。これまでの文脈から外れるかもしれないが、これもこの歌集の一面である。
植木算は木を描きながら解くのだと子は言う枝に葉をつけながら
よき母でありしことなく春の雨傘もたすことを今朝も忘れて
これらの歌にはこだわりがない。母親であることの喜び。母親であることを疑わない充足。そのことが歌から素直に伝わるのである。
私たちは、さまざまに分節化された世界に暮らしている。たとえば、男性と女性。理性と感情。上位と下位。分節化されたこれらは再構成されて、世界をさらに分節化する。男性は理性的で社会の上位に位置するのが妥当であり、女性は感情的なので男性に従った方がいい、というように。世界は基本的に恣意的に分節化される。
美人の基準一つとったってそうだ。かつての日本では、ふくよかな吉祥天女像みたいのがもてはやされていたのであり、スリムをよしとするようになったのは明らかに欧米文化が到来してからだと思われる。吉本隆明風に言えば、世界は共同幻想であり、私たちはいつ、どこで、だれが、決めたわからない規範に従って生きているとも言える。そのような分節化を、意図的に少しでもずらすことができれば、世界は新しくなる。そのためには、いったん世間の定めた分節化から外れる試みが必要になる。とは言え、私たち自身が既成の分節化にどっぷり漬かっているわけで、まずは私自身を解放しないことには先に進まない。
歌集『未明の窓』の作者が、教員である自己規範から逃れようとしたのは、表現者にとって必須なことだろう。
わたしたちは、気がつかないけれどわたしたち自身を縛りつけているわたしたちの規範から、逃げたいと思うことがないだろうか。現代社会で普通に暮らす人たちは、普通に生きるためには仕方がないと割り切っているようでいながら、少なからず不如意感を抱いているのではないか。
少し前に刊行された歌集であるが、真中朋久の『火花』を読んでその思いを深くした。
生年月日はマークシートをぬりつぶす住所氏名に文字書きしのち
太陽にかざすにあらず扉に触れて手指は今し静脈を読まれつ
一首目は現代的なシステムの愚かしさを揶揄する。二首目は、個人の認証システムなのだろうが、得体の知れないものにみずからの生死を握られたかのような不気味さをうたう。ここには現代社会に対する違和感が紛れもない。
風力にも太陽光にも商機ありと真顔ならむ声 顔あげず聞く
とりあへず頭金だけ用意すると衝立のむかうに声は過ぎたり
世界が資本主義によって回るということは、利潤の追求にいとまがなくなることに他ならない、とわかっていても、そうしなくては普通に暮らしていけないとしても、得心できないのだ。
私は死者であるゆゑ呼ばれればよきこともよからぬこともするべし
ひとのいのちをむさぼつて生きてゐる おまへも おまへもとうに死者
ごく普通の勤労者が、普通に働いて暮らすということが、どこかの、誰かの貧困と不幸の上に成り立っていることに、作者は敏感である。現実に違和を唱えながら、自分がその社会を成立させる一員であることに、作者は自覚的である。そして、システムの要請を、喜んでするのではなく、よからぬことをするのだという自覚が、既成の分節化とは異なる分節化を作者にもたらすと思う。