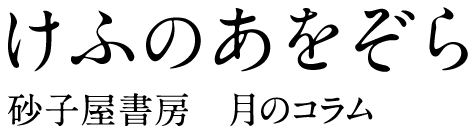生活に動機をもとめ、それを素材に歌を詠む人は、圧倒的に多い。そして、面白い。他人のことなのに。どうしてなのか。
花山多佳子歌集『晴れ、風あり』を読む。
いま書きしハガキも消えて雨の日のまひるの部屋をわれはもとほる
思い当たる節がある。さっきここに置いておいたのに……。でも、「消えた」と言ったり、思ったりする人はいないだろう。忘れたなら思い出すすべもあろうが、消えたものは取り返しがつかない。戸惑う度合いが違う。すべがなくて、それでもうろうろするから「もとほる」のである。
夜の雨はまなこを侵し鼻を浸し溺れさうなり自転車を漕ぐ
ただならぬ事態が出来している。氾濫する川にのみ込まれたか、悪人の手にかかったかとしか思えない。そんな言いようなのであるが、実際は雨中自転車走行之図なのである。言葉と実態との落差がユーモアを醸すと言えば、それはそうだが、本人が大真面目で作歌に取り組まないとやらせになる。
行人坂の近くに部屋を借りるといふ娘の一人暮らしにときめく
家を出る娘の荷物に混ぜておくパン屋より今日もらひしカップを
まさかここに娘は住むのか穴あける廃屋のやうなこのアパートに
母と娘の関係は、父親には測りがたいものがある。朝には罵り合っていたかと思うと、夕べには連れだって買い物に行く。1首目の「ときめく」が可笑しい。2、3首目を読めば、母が娘の一人暮らしを
案じているのがわかる。だが、それはそれである。歌人たる母が、一人の独立した世界を心ひそかに臨むのは、わからなくない。絵心があり、自身も歌人である娘であってみれば、母の気持ちもわかるというものだ。これは娘にふさわしいのではないか、という心遣いも母親ならではのものだろう、「パン屋より今日もらひしカップ」という措辞にはリアリティーがある。因みに「行人坂」は、東京都目黒区の地名。神田・浅草など江戸の大半を焼いた「明和の大火」(1772年)の火元である大円寺のあったところ。
年明くる十分前に現れて眠りて去りし息子はまぼろし
二日後にまた現れて地元の子と飲みにゆきたる息子は現
次は息子の歌。息子は新年の挨拶だけにちょこっと戻ってきたのである。若者にとってカウントダウンと新年は一大イベントの日である。そうそう親のことは構っていられない。でも、我が家の新年のしきたりは守らねばならぬというので、こういうことになったのだろうと推察する。息子に言わせれば律儀に筋を通したのであり、父親にはその気味合いはわかる。だが、母親にとっては、神出鬼没にしか思えない、そのあたりの消息が面白い。
貸本屋には少女漫画を借りて来しころ思ひ出す赤き躑躅は
おねえちやんと呼びゐし叔母のもう居らず誰と語らむ昔のことを
回想の歌2首。貸本屋世代には懐かしいが、それはひとえに「赤き躑躅」ということばの喚起力による。いまだって躑躅は咲くが、この歌の躑躅は貸本屋までの道のりを想起させるのだ。雨が降れば、水たまりができて、晴れた日には木でできた突っ掛けを履いていったに違いない。「貸本屋」「少女漫画」「赤き躑躅」のイメージ連合のなせるわざである
「叔母」は玉城肇の娘にして、玉城徹の姉妹。この叔母は、普通の主婦であったようであるが、玉城肇の著書をあまねく収集していたという。次のような歌が歌集にある。
つづまりは妥協を余儀なくされるゆゑハンストはするなと祖父の言ひゐき
作者に向かって言ったとおぼしいが、作者は何歳ぐらいだったのだろう。
「叔母」の歌に戻るが、年がゆけば、知りびとが失せるのは世の習いとしても、寂しいことに変わりはない。その寂しさの本質を下句の「誰と語らむ昔のことを」は言い得ている。
随縁ということばがある。仏教では大切にする言葉であるが、その深い意味はさて置き、さまざまな縁が織りなす小さな物語が日常である。この歌集にも、物忘れ、雨中の自転車走行、娘の独立、息子の奇行、叔母の死などなど、読者と地続きの生活が歌われる。その生活が詩になる機微について、今まで述べたことのほかに、これも大事なことかもしれない、と思いついたことを記す。
めぐってくる日頃の縁に、作者はどう向き合っているのか。
ベートーベン第九流しつつ夜を来る灯油販売車待つはわれのみ
師走の寒い夜である。作者は、携帯用の2リットル入り赤ポリタンクを地面に置いて、灯油を満載したタンクを荷台に乗せた軽トラックを待つ。それも一人で待つ。かなりわびしい。そこへ、その場の雰囲気にこれほどふさわしくないものはない、というベートーベン作曲のかの「第九」が流れてくる。何の因果でこんな時に「第九」を聞かされなくてはならないのか。結句の「のみ」にわたくしはそう感じ、思わず笑った。
ところで、日常とはかかることの連続ではないのか、とも思う。いままでの歌についてつらつら思うと、思いもかけずこのような事態が出来し、歌にするしかないでしょう、という作者の声を聴くような気がする。絶対受動の能動的作歌とでも言おうか。このような作者の姿勢に気づくと、次のような歌が意義深く思われる。
「勇気→行動→感動」と出るケータイの迷惑メールをただちに削除
毎日が気ぶっせいなあなた、感動的な日々に変えませんか。さあ、勇気をもって、行動に移しましょう。まずは、ここにアクセスして、さあ早く!そんなニュアンスがぷんぷんするメール。作者がそんなメールにアクセスするはずがない。この歌は、「勇気→行動→感動」という呼びかけが、いささかでも有効らしい現代社会の現実に、的確に照準しているところがすごいのだ。「勇気」や「行動」が善であり、「感動」が幸福であるという価値観をおしつけるものを、作者は断固として肯わない。
われわれの世代のやうにアジることなきゆゑ湯浅誠を信ず
多くを言うこともない。そのとおりだと思う。わたくしは、この歌を読んで、山口瞳が書いた学徒出陣式の一節を思い出す。行進する学生に向かって、スタンドで「帽振れー」と叫んだ大人を絶対に許さない、と。
次の歌が好きである。
朝あさを水そそぐなりいつしかに雑草のみとなりし鉢にも
ある時に、鉢植えの花を買い求めた。毎朝、水やりを欠かさなかったが、いよいよ枯れてしまった。鉢には草が芽を出し、勢いをつけてきた。雑草だけの鉢であるが、水やりは欠かさない。奇行である。花にもいのちがあるから、という人道主義の歌ではあるまい。もちろん他の花に水をやるついで、ということもあろうが、それだけではないだろう。花が咲いているうちは水をやり、枯れたらやらないという、あるかなきかの功利性が自分に許せないのだと思う。
どんな現実がめぐってくるかは、誰にだってわからない。それを受けとめた上で、自分一人のやり方を通す。そんな生活の流儀を素敵だと思う。
新聞にはいろんなことが書いてある。IS国の拠点モスルへ総攻撃が始まっているらしい。シリアでは小学校が空爆に曝された。香港の独立派議員は議員資格が奪われそうだ。日銀が大量に刷ったお金は誰の懐に入ったのかわからない。小さい子どもが親に虐待を受けている。世界でも国内でも、事件の起きない日はない。
作者もその現実に生きている。
近づけば道に飛び立つ鶺鴒が舌打ちのごとき声を残せり
何事もなかつたやうだ昼も夜もつけつぱなしのテレビを消せば
鶺鴒に舌打ちされる自分とは、この現実の中で無力であることに自覚的な自分である。2首目は、実は東日本大震災をモチーフにした歌なのだが、実際の事件を伏せても、今日の情報社会のうそ寒い現実が窺える。作者には忸怩たる思いがあるのだ。
作者の父である玉城徹の遺した言葉が、わたくしには忘れがたい。世界中がどんな不幸でも、自分だけは幸せを求めなくてはならない、と。作者にはかかわりのないことかもしれないが、この歌集は、そんなことを思わせたのだった。