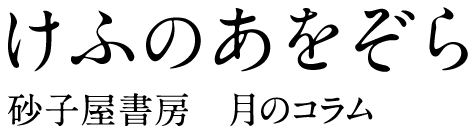4月10日(木)
現代歌人協会理事会。コロナ禍以来オンラインで行っているが、4月は年間の会計を話し合う関係で対面で開催される。
昨年まで会場は学士会館だったが、今年は喜山倶楽部に変わった。学士会館は建て替え工事でしばらく使えない。すなわち、全国短歌大会や公開講座、総会や授賞式の会場もすべて代わりをさがさなければいけない。
同じタイミングで中野サンプラザの建て替えも始まったばかり。各結社の全国大会などもそうだが、ただでさえ会場となるようなホテルはインバウンドの影響で値上がり傾向にあり、なにかと悩ましいのだった。
会場を出るとしっかりと雨が降っていた。慌ててコンビニで傘を買ったが、建物内の中華料理屋で有志の打ち上げをしているうちに小雨になり、新しい傘に雨粒が転がるのを見上げながら帰った。
4月16日(水)
今年度の現代歌人協会公開講座が始まった。
現代歌人協会は、入会するのに現会員からの推薦と委員会の選考、総会での承認を経なければいけないこともあり、外から見ると取っつきにくい組織なのだと思う。しかし、公開講座は会員でなくても聴講できるし、むしろ事業の一環として会員の払う会費から赤字分を拠出している、外部に「お得」な講座なのだった。
テーマは「協会賞歌集を読み返す」。過去の現代歌人協会賞受賞歌集を取り上げ、時代と歌人と歌集について講演と対談を行う。
3年目となる今年度の第1回は小野茂樹『羊雲離散』(1968年)。講師は久我田鶴子さん、対談に高野公彦さんにご登壇いただいた。
小野茂樹(1936年~1970年)というと、
あの夏の数かぎりなきそしてまたたつた一つの表情をせよ 小野茂樹『羊雲離散』
があまりにも有名である。
30年ほど前の若手歌人はだれもがこの歌と
するだろう ぼくをすてたるものがたりマシュマロくちにほおばりながら 村木道彦『天唇』
を(当時村木さんは短歌を離れていたので)遠い晩夏光を見つめるようにうっとりと愛唱していた。
私はお恥ずかしながら恋愛の機微というものに昔から疎く、「こういう表現をしたら読者はこういう反応をするものなのだな」という理屈で恋の歌を読んでいるのだが、「あの夏の数かぎりなきそしてまたたつた一つの表情をせよ」の母音の使い方、指示語・接続語の使い方などの鮮やかさはひとつの恋の歌の典型なのだと思っている。
講演も対談も素晴らしく、今まで遠くの晩夏光だった小野茂樹が人のかたちをして感じられるようになった。オンライン聴講のための動画を作りながら、ふと、「間に合った」という感覚が湧き上がってきた。
余談だが、終了後久我さんと高野さんを三顧の礼でお誘いしまくり、中華料理店に行った。
久我さんに「(小野茂樹と久我さんの師である)香川進ってどんな方でしたか?」とお尋ねし、「ひとことで言うと怖いおじいさん。だけど、懐がひろくて困ってる人がいると手助けできないかいつも考えていたひと。」と教えてもらったり、高野さんから「佐藤佐太郎と宮柊二と吉野秀雄が吉野秀雄の家で飲んでいたとき、佐藤佐太郎(師は斎藤茂吉)と宮柊二(師は北原白秋)がどちらの師がより優れているか揉めはじめ、取っ組み合いになってしまった。そこに席を外していた吉野秀雄が戻ってきて、もつれている二人の上にどっかりと座って、會津八一にきまっとる! と言った」などと聞いたりした。
ゴッホの絵を見る時にゴッホの人生を思うように、ベードーヴェンの音楽を聴くときにベートーヴェンの人生を思うように、短歌も作者の姿が見える方が面白い。
4月19日(土)
「短歌人」編集委員の本多稜さんの歌集『時剋』の批評会。小島ゆかりさん、大井学さん、内山晶太さんとともにパネリストを務めた。
一年間の闘病の様子をまとめた歌集で、今年度の斎藤茂吉短歌賞を受賞している。
本多さんには初めてお会いしたが、痩せてはおられたもののたいへんお元気そうでほっとした。
緊張してパネルの内容はおぼろげなのだが、後半の会場発言の充実がこのところの批評会ラッシュの中にあっても特別であった。
中でも川野里子さんのご発言にドキッとした。
「歌人の中には定型を愛している人と憎んでいる人がいる。本多さんは間違いなく愛している人である。
定型を愛している人は病を乗り切ることができる。
では、定型を憎んでいるひとは病とどう対峙していくのだろうか。」
定型を愛している人と憎んでいる人。
私はたぶん定型を愛している。だが、同時に憎んでもいるのではないかとも思う。誰もが簡単にできましたと言えてしまうその情緒的なずるずるにゾッとするときもある一方で、この31音は限りなく美しく愛おしく完璧な形だと思うときもある。
もう一つ、著者の挨拶も心に残った。おそらく先の川野里子さんの言葉を受けてのものだろう。
「病を得たとき、五七五七七は完全体だと思った。定型に生きてもらい定型に自分を引っ張り上げてもらおうという気持ちになった。」
これらは、批評の言葉としては不安定かもしれない。だが、実作者としてはいつも心に置いておきたい言葉である。
4月24日(木)
空穂会の年に一回の会合。
空穂会は空穂の関係の結社が作る会で、現在は「音」「かりん」「国民文学」「濤声」「富士」「まひる野」「沃野」の7つの結社で構成されている。
空穂の忌日は4月12日なので4月に開催されるが、空穂の誕生日のある6月に開催された例もあったと記憶している。
かつては「槻の木」が幹事を務めていたが、「槻の木」解散後はいちおう「まひる野」が代表、幹事は毎年持ち回りで開催されることになった。
コロナ禍を挟み、昨年が数年ぶりの開催だったが、今年は昨年より人数が増え、139名の参加、盛会であった。
メインの講演は、馬場あき子と島田修三の対談。『卓上の灯』からそれぞれが7首選をし、それを読みながら空穂についての話を進めていった。馬場さんは20歳前後の若い頃から空穂にかわいがられていたという。島田は空穂と会ったことはないものの、章一郎から空穂の話を聞いていて章一郎越しの空穂の実像を知っている。
それぞれの空穂像を補足し、補正していく対談は大変面白く、ここでもふたたび、「間に合った」という感慨を感じた。
4月29日(火)
「かりん」所属の谷川保子さんの『おもてなしロボ』の批評会に参加。
パネリストは大森静佳さん、大松達知さん、花山周子さん、松本典子さん。
障害児教育に携わる作者の対象との接近について賛否両面から語られ、「他者」と「われ」の関係について考えさせられた。
先週に引き続きここでも川野里子さんの会場発言が印象に残った。
「寄り添うことは、一方で他者を侵犯する行為でもある」。
全くそうだと思うと同時に、それでも歌を作り続けるにはどうすべきかを考えている。
ところで、『おもてなしロボ』だけでなく、このところ職業詠がきっちり収録された第一歌集が増えてきた気がする。
獣医 久永草太『命の部首』
新聞記者 森澤真理『地吹雪と輪転機』、加古陽『夜明けのニュースデスク』
医師 林祐一『ポリクリノート』
教師 貝澤駿一『ダニー・ボーイ』
日本語教師 米倉歩『日本語中級1クラス』
医療相談員 丸地卓也『フイルム』
そういえば、今年の塔新人賞の授賞者は杜氏さんだった。
さらに、職業詠は多くはないが土地が作品のテーマのひとつになっている歌集も見られる。
屋良健一郎『KOZA』
滝本賢太郎『月の裏側』
天野陽子『ぜるぶの丘で』
一方で小原奈実『声影記』、金田光世『遠浅の空』などポエジーが中心である優れた歌集もあり、第一歌集の幅が広がっているように思う。
今後の展開を楽しみにしている。
※ はじめの更新で吉野秀雄宅で取っ組み合いをしたのを「香川進(師は前田夕暮)」と書いてしまいました。正しくは「佐藤佐太郎(師は斎藤茂吉)」でした。記憶違いで大変申し訳ありません。
香川進が宮柊二と取っ組み合いをしたのは香川進の家のことで、別の機会だったそうです。