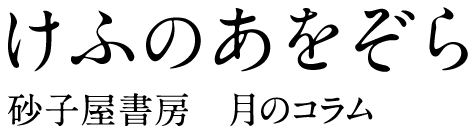2月7日(金)
小島ゆかりさんの毎日芸術賞のお祝いに椿山荘に行く。目白駅からバスに乗りつつ、このあたりに空穂は住んでいたのだな、と親しく思う。
華やかな会場だった。
昨年よりユニクロが協賛に入り40歳未満を対象とした賞が創設されている。今年の受賞は映画「ナミビアの砂漠」の監督山中瑤子さん。彼女の受賞の挨拶が特に心に残った。
この国で映画を撮っている若い世代は映画を撮っているだけでは生活できず、山中監督自身も2024年に初めてアルバイトをせずに暮らせたのだという。暮らせたと言っても今も果物などはとても買えない。その立場からすると映画の1800円という料金は高額で見てほしいとは気楽に言えない。けれども、それだけ取っていても作る側は生活できない。八方塞りでどうしていいか分からない。
スピーチを聞きながら、これは、短歌の世界も同じだなと思う。
例えば歌集を出すには大きなお金が動く。「車一台分」という比喩で大雑把に伝わっているのは装丁や部数によって変わるからだろう。では、それだけの支払いを受け取る版元は莫大な利益を得ているかというとそうではなく、ほとんどが紙代やインク代、印刷代や製本などの支払いに消えるのだろう。
雑誌だってそうだ。短歌雑誌への寄稿の報酬が安い、なんとかならないか、という書き手の不満をしばしば見聞きするが、例えば10万部出している雑誌と1000部の雑誌ではページ単価が同じでも100倍の差が出るわけで、短歌雑誌が売れない以上原稿料は上げられない。
結社誌などは、選歌や割付、校正を含めたすべての労働力をボランティアで賄ってなおやや赤字、寄付でとんとんにしているのである。
ため息の出る状況であるが、ではほかのジャンルはどうかというと、舞台の成功のために歌を歌ったり、ピラミッドを掘るためにクイズ番組に出たりといったことはままあるだろうし、やりたい仕事だけできるわけではないだろう。
なにより怖いのは「売れる」ことだけを評価の中心に据えることだろうと思う。
そもそも芸術や文学はパトロンとかタニマチという存在と不可分なのかもしれないが、そのような篤志家は多くはない。
2月13日(木)
武蔵野大学の公開講座に馬場あき子さんが登壇されるというので見に行く。1月28日が誕生日で97歳になられたそうだが、とにかくお元気で溌溂としておられる。
おそらくは30分の枠であろう対談を、45分ほぼおひとりでお話になりストップをかけられていた。力強い。お声をきくだけで力が湧いてくる。
講座のタイトルは「土岐善麿新作能の世界」。
戦後始めた短歌と能の、どちらの会に行っても重鎮として善麿がいたのだという話、その経験をしたのは馬場さんだけではなかろうかと思った(富小路禎子もそうだろうか)。
善麿の評価の低さ、というより読まれなさは生前の篠弘も嘆いていた。
善麿はとにかく歌集が多く、また仕事が多岐にわたるので全体像がつかめないのだが、こうした機会に少しずつ読んでみたいと思った。人の話を聞くのは好奇心を掘り起こされるようで嬉しい。
レジュメは手書きだった。きれいに持ち帰り、新しいクリアファイルにいれた。
2月14日(金)
第36回歌壇賞授賞式。
第39回俳壇賞との共催で、とても盛況だった。
俳句と短歌の両方をされている人も多いが、私は俳句はまったく分からない。受賞者や選考委員を含めて俳句の人は全体に年齢層が高く感じた。なんとなく外向きで明るい感じもする。七七が湿っぽいのだろうか。
講評の中で選考委員の吉川宏志さんは、
「うまい」ということがまるで悪いことのように扱われることがあるが、「うまい」歌があるから短歌の世界がある。「うまい」歌は大切。何を詠むかということはその都度変わるので、どう詠むかが大切。
と述べられた。
私は「うまい」は誉め言葉にしか使わないが、「うますぎる」という言い方をすることはある。まとまりすぎていわゆる「短歌らしい短歌」になり、その人らしさが見えないときである。「うまい」だけでもそのニュアンスを感じてしまうのだろうか。不安になってきた。
高野公彦『うたの前線』(1990年・本阿弥書店短歌ライブラリー③)に、「破調、乱調」という文章がある。
高野は定型から外れた歌を ㋑破調の歌 ㋺乱調の歌 ㋩自由律短歌と大別し、定型意識を保ちながら、大幅に字余りや字足らずが生じたものを「㋑破調」、同じく定型意識を保ちながら、定型からの外れ方が字数の幅を越えて、句構成の破壊に至ったものを「㋺乱調」、はじめから定型意識のない、あるいは希薄な短歌ふう短章を「㋩自由律短歌」とし、乱調の例として
不意に耳の痒くなり思い継げる感傷逸れぬたいしたことではない 宮 英子
青葉暗しわが鬱くらしと言ひ出づるにウッソーと友の笑ふ 宮 英子
これらの歌は破調というより乱調であり、初めて読んだときは戸惑うが、言うに難しい面白さ、命の脈動、命のエネルギーを感じて魅力的だと述べる。
さらに、
打発止と勝手口よりあがりざま軽口の楽しさ互みに伴侶 河野裕子
はかないほど早く大きくなつてしまひいよいよもう追ひつけない 河野裕子
は、ともに破調、あるいは後の歌は乱調かと述べこう続ける。
「内面の渾沌を、定型といふ柄杓で掬ひ上げる。感情やらなにやら分からぬ内面の渾沌が、柄杓の中でたぷたぷ揺れ、また、柄杓からぽたぽたこぼれる」
そして、定型から外れた歌というのはこうした「たぷたぷ、ぽたぽたの歌たち」だろうと言うのである。
注目はその後である。
死は生身死なば死もまた死ぬるなりまみづの色の月のぼり来ぬ 河野裕子
昨日まで生きゐしひとの歌集閉ぢ物買ひに出づ夏日ざんざん 河野裕子
「河野愛子の死を悼む、すぐれた歌である。よく見ると、二首とも定型ぴたりだ。このやうな定型の歌に混じると一層⑫や⑬(※「打発止と」「はかないほど」の2首)の破調も魅力が加はる。破調・乱調の歌を支へるのは、定型なのである。」
定型あっての破調、それは素直な「うまい」歌あっての挑戦作につながるだろう。
やはり「うまい」は誉め言葉であってほしい。
2月26日(水)
定例の空穂全歌集を読む勉強会。
『空穂歌集』でなぜ空穂が句読点を多用していたかを知るためあれこれ調べてみるが、あまり収穫はない。結社の用事で師である島田修三から電話があったので聞いてみたが「君たちももう50代なんだからのんびり通読なんてせずに空穂を読むなら『鳥聲集』とか『土を眺めて』とかをしっかり読み込めよ」と言われてしまう。本当にその通りだと思う。
桜楓社の『和歌文学講座3歌壇・歌合・連歌』に山崎敏夫が「六 歌壇的現象と社会的事実」として明治32年に注目している。
曰く、この明治32年という年は改正条約の実施の年なのだという。
日米修好通商条約は明治44年の小村条約と言われる改正で関税自主権を回復したが、それ以前に陸奥条約と言われる改正が行われており、それが1899(明治32)年に発効されている。これのことだろう。
山崎は明治の新しい歌は海外文化からの影響と、それに対しての国民的自覚という両者の渾融から生まれると指摘する。
明治32年は竹柏会が成立、また根岸短歌会も成立、さらには翌年の「明星」創刊に先駆けて東京新詩社が誕生したのもこの年だという。
明治31年は落合直文が糖尿病を患った年なのでそういった理由もあるのではないかと思うのだが、現在ある結社の多くが戦後10年の間に生まれていることを考えても時代の空気というものはあるのだろう。
先の俳壇賞の講評の中で星野高士さんは良い俳句について3つの要件を述べた。
1、 時代に敏感であること
2、 発見があること
3、 詩があること
これらは短歌にも当てはまる。生きている人間が作る以上作品にはなにがしかの時代の影響があることは当然だが、表現者としてはさらに前のめりに時代に切り込む気構えが必要であろう。
*
俳句と言えば、先日の歌壇賞・俳壇賞の授賞式であまりに俳句の人が多かったので、いったいどれくらい人口が違うのだろうと検索してみた。
「レファレンス協同データベース」に同様の質問があるが、結論としてははっきりしなかった。そもそも「短歌・俳句を詠む人」の定義によって変わるという結びに納得をするものの、だいたいでいいから知りたいと「現代俳句協会」のホームページを見てみた。
会長挨拶のなかで会員数が4200名と書かれている。
「現代歌人協会」のホームページでは900名余りとあるので、5倍近くということになるが、推薦と理事会の選考、総会の承認を経て会員になる「現代歌人協会」に比べて「現代俳句協会」は推薦のみで入会できるようなので、名前は「現代歌人協会」のほうが似ているがむしろ「日本歌人クラブ」と比較する方がよさそうだ。
「日本歌人クラブ」のホームページを見ると会員数は約2000人とあるので、大雑把に倍くらいというところだろうか。なるほどと思った。